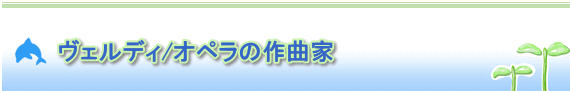|
19世紀を代表するイタリアのオペラ作曲家。
村のオルガニストに音楽を習ったが、音楽の基礎的な教育は不十分だったようで、ピアニストとしてミラノ音楽院への入学はできず、作曲へ転じる。『ナブッコ』(1842年)で大成功を収め、同年生まれのドイツの作曲家ワーグナーと人気を二分する様になる。
『ナブッコ』が初演された頃、イタリアではリソルジメント運動(この場合、イタリアの独立運動を指す)が盛り上がっていた。『ナブッコ』はユダヤ人を虐げるバビロニア人の物語であり、この内容は当時のイタリア人の受けていた境遇と似ていた。特に合唱曲<行け、我が思いよ、金色の翼にのって>は今日のイタリア人にとっても「第二の国歌」的な意味合いを持つ。『ナブッコ』で主演したソプラノ歌手・ジュゼッピーナ・ストレッポーニはヴェルディのよき理解者・伴侶となりヴェルディを支えた。
『ナブッコ』以降、『マクベス』(1847年)、『ルイーザミラー』(1849年)、『リゴレット』(1850〜1851年)、『トロヴァトーレ』(1852年)、『椿姫』(1853年)、『仮面舞踏会』(1857〜1858年)、『ドンカルロ』(1865〜1866年)など次々と傑作オペラを生み出した。
エジプト総督の依頼により『アイーダ』(1870年作曲)が作曲された後、ヴェルディは作曲意欲が減退していたが、作曲家でもある台本作家ボーイトと協力し再び作曲意欲が復活。『オテロ』・『ファルスタッフ』などの傑作を生み出している。
国会議員としても活動し、晩年は音楽家のための養老院「憩いの家」を設立した。
【代表作】
<オペラ>
『ナブッコ』(1841年作曲)、
『マクベス』(1846〜1847作曲)、
『ルイーザミラー』(1849作曲)、
『リゴレット』(1850〜1851年作曲)、
『トロヴァトーレ』(1852年作曲)、
『椿姫』(1853年作曲)、
『シモンボッカネグラ』(1856年〜1857年作曲)、
『仮面舞踏会』(1857年〜1858年作曲)、
『運命の力』(1861年〜1862年作曲)、
『ドンカルロ』(1865年〜1866年作曲) 、
『アイーダ』(1870年作曲)、
『オテロ』(1880年〜1886年作曲)、
『ファルスタッフ』(1890〜1892年作曲)
<宗教曲>
『レクイエム』(1874年作曲)
|